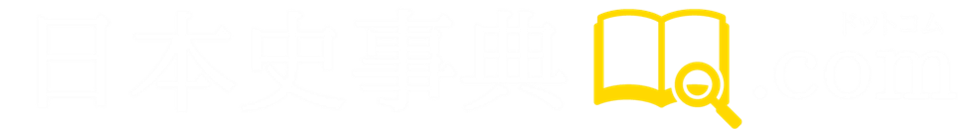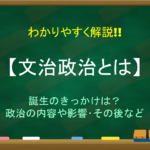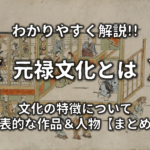“奥の細道”といえば、聞いたこともあり、ある程度簡単に説明出来る人も多いのではないでしょうか?
社会の歴史というよりは国語の授業で学んだ人の方が多いかもしれませんね。
ここでは国語で概要を学んだ『奥の細道』について、歴史的見解を含め確認していきたいと思います。
目次
奥の細道とは?

(左「芭蕉」と右「曾良」 出典:Wikipedia)
奥の細道とは、江戸時代の俳人『松尾芭蕉』が、尊敬する西行の五百年忌にあたる1689年(元禄2年)に江戸を出発し、東北から北陸地方を実際に旅し、それぞれの地の様子などを文章や俳句でまとめた旅行記、所謂『紀行文』のことです。
奥の細道が書かれた当時の時代

“奥の細道”がまとめられたのは、どのような時代だったのでしょうか。
①元禄の世
元禄時代は、有名な五代将軍徳川綱吉の時代ですね。
江戸初期の様々な混乱も落ち着き・・・
- 政治は文治政治へ転換
- 新田開発などにより農業生産力がUP
- 海運業も盛んになり商品流通が発達
- 貨幣経済も発展して京都大阪などの上方を中心とした町人文化である元禄文化が栄えた時期
となります。
②当時の有名人
松尾芭蕉とその「奥の細道」は元禄文化を代表するものですが、
他にも・・・
- 浮世草子「日本永代蔵」の『井原西鶴』
- 浮世絵「見返り美人図」の『菱川師宣』
- 「紅白梅図屏風」の画家『尾形光琳』
- 「曽根崎心中」の浮世絵作家『近松門左衛門』
など有名人が沢山います。テストで一度は見たことがある人ばかりですね。
奥の細道の作者「松尾芭蕉」について

(松尾芭蕉『三日月の頃より待し今宵哉』 出典:Wikipedia)
①日本史上最高の俳人
1644年三重県伊賀市で誕生した松尾芭蕉は、19歳から俳句をたしなみ『俳諧師』として身を立てるべく江戸へ移り、その才能を開花させます。
当時の俳諧の一派であった談林派の宗匠(和歌や連歌、文芸などの師匠)となりますが、後に蕉風俳諧を打ち立て、俳諧を単なる言葉遊びではなく、自然や庶民の情を含んだ表現豊かなものへと高めていきます。
「俳聖」と呼ばれる芭蕉が俳諧へ与えた影響は大きいものでした。
②忍者?隠密?謎の人物
“奥の細道”の移動距離と行程を考えると、一日平均16㎞、最大50㎞近く歩いたとされ、健脚だったとは言え45歳の芭蕉には厳しかったと推測されます。
その為「芭蕉は忍者だった」という説もあります。伊賀出身だからでしょうか。
また、百姓出身であるにもかかわらず「松尾」姓をもらっていることから、幕府との繋がりがあり、旅自体が幕府の隠密行動だったとする説もあります。
これらの真偽は定かではありませんが、尊敬する平安期の歌人『西行法師』の足跡や古歌の名所・旧跡など【枕歌】を巡るための旅だったとするのが通説となっています。
奥の細道の内容

(河合曾良 出典:Wikipedia)
芭蕉が弟子の河合曾良(かわいそら)を連れて江戸を出発、東北~北陸をめぐり岐阜大垣に至るまでの全行程2400㎞、約150日間の旅の旅行記である“奥の細道”はその土地を文章で説明し、俳句を一つ詠むという形式でまとめられています。
①冒頭と序文
≪月日は百代の過客にして行きかふ年もまた旅人なり(月日は永遠に旅を続ける旅人のようなものであり、毎年来ては去る年もまた旅人のようなものである)≫で始まる冒頭は非常に有名ですね。
その後の序文では船頭や馬方を例に出して「人生とは旅である」とする人生観を表しています。
②ルート
江戸の深川を出発し、栃木県の日光から松島、平泉にいき、日本海側の山形を通り新潟から金沢に入ります。
その後福井を通り岐阜の大垣に到着。その後伊賀に出発するまでが“奥の細道”のルートになります。
奥の細道を巡る

旅の出発から終了までの色々なエピソード、有名な句をいくつかみてみましょう。
①旅立ち
1689年3月27日、芭蕉は曾良と共に出発します。旅立ちにあたりこの句を柱にかけて家との別れと新しい住民への挨拶としたそうです。
「草の戸も住み替わる代ぞ雛の家」(このわびしい草庵も隠者の住まいから世俗の人の住まいに代わり、雛人形など飾る楽しい家になることだろう)
また旅の最初に・・・
「行春や鳥啼魚(とりなきうお)の目に泪(なみだ)」(春が過ぎ去ろうとしているが、それを惜しみ鳥は鳴き、魚も目になみだを称えているようだ)
と詠み、親しい人々と別れる寂しさと共に、これからの旅への期待感を含ませていました。
②日光(茨城)~黒羽(栃木)
出発してから船に乗って千住に渡り、日光街道の草加を通って日光東照宮に詣でます。
その後、栃木の黒羽町では大歓迎を受け、旅の中でも長期滞在となりました。
滞在中には芭蕉の師である雲巖寺の仏頂和尚(ぶっちょうおしょう)を訪ね、さらに九尾の狐伝説の『殺生石』、尊敬する西行法師が立ち寄ったとされる『遊行柳』を見学し、感無量だったようです。
殺生石は那須高原の史跡として今も見に行くことが出来ますので、安全に気を付けて訪れてはいかがでしょう。
③白河の関(福島)~松島(宮城)
黒羽からさらに北に進み、有名な【白河の関】へ到着します。
白河の関は東北の玄関口とされ、芭蕉は古歌や故事を偲ぶのに夢中で句を詠む余裕がなかったとされています。
その為、弟子の曾良が句を詠みました。
「卯の花をかざしに関の晴れ着かな」(かつてこの白河の関を通るときに陸奥守が敬意を表して衣装を代えたというが、そこまでは出来ないけれどもせめて卯の花を頭上にかざして敬意をしめそう)
その後日本三景のひとつ松島に到着します。松島は旅の当初から“旅の目的“と言われている場所でした。
塩釜から舟で松島入りしたようで、この航路は現在も運行している人気航路のようです。
芭蕉は絶景を眺めた時には詩作を控えるという中国の文人達の姿勢に倣い、ここでも句は残していません。
④平泉(岩手)~出羽(秋田)
石巻を経て平泉に入りますが、ここは旅の折り返し地点でもありました。
ここでの句は非常に有名ですね。奥州藤原氏滅亡の地で、かつての戦いと悲劇の物語に思いをはせ
「夏草や兵どもが夢の跡」(ここはかつて源義経や藤原氏が栄華を夢見たところだけど、今はただ夏草が深く生い茂り、はかなく散った兵の事を哀れに感じる)
また、藤原氏の霊廟金色堂の姿を見て「五月雨の 降り残してや 光堂」(毎年降るはずの五月雨がこのお堂にだけは降らずに残していたのだろうか、光堂という名の通り輝いている)という句も残しています。
その後奥羽山脈を越えて出羽国で山寺(立石寺)に立ち寄った際に、「閑かさや岩にしみいる蝉の声」(あたりは静かで物音ひとつせず静まりかえっている。その中で蝉の声だけが岩にしみいるように聞こえて、静寂さをいっそう引き立てている)という有名な句が詠まれました。
⑤最上川~象潟(きさかた)
日本三大急流の一つである最上川を下り最北端の地、当時は松島にならぶ景勝地であった秋田の象潟に到着します。
ここでは表現が綺麗な句として「象潟や雨に西施(せいし)がねぶの花」(象潟の海岸地にて雨でしおれたねむの花が咲いているが、まるで中国四大美女の一人西施がうつむいているようだね)と詠んでいますが、花の幻想的な美しさがとてもよく伝わります。
⑥北陸道~大垣
再び日本海沿いに南下し、佐渡島を臨んで悲しい佐渡の歴史を偲びつつ、日本海の荒波を詠みました。
「荒海や佐渡によこたふ天河(あまのがわ)」(荒く並立った海の向こうに佐渡島が見える、その上に天の川がかかって雄大な景色である)
その後山中温泉で、病気療養の為に伊勢に行く曾良と別れます。一人旅となった芭蕉は寂しげな句を残しています。
そして敦賀を通り最終着地である大垣に入り、ここでは多くの弟子たちがお出迎えをしてくれました。
曾良も療養から戻ってきていました。
そして、また再び大垣から伊勢神宮の遷宮を拝観しようと船に乗り、最後の句を詠んで“奥の細道”が終わります。
「蛤(はまぐり)のふたみに分かれ行く秋ぞ」(伊勢の蛤の「ふた」と「み」がなかなか切り離せないように離れがたい思いをふりきって、この親しい人々と別れを告げ、私はまた旅立とう、この秋が過ぎて冬に向かう季節に)
この句は旅立ちの最初の句(行春~)と(行秋~)で対になっており、諸行無常の観念を示していると言われています。
奥の細道から受けたもの
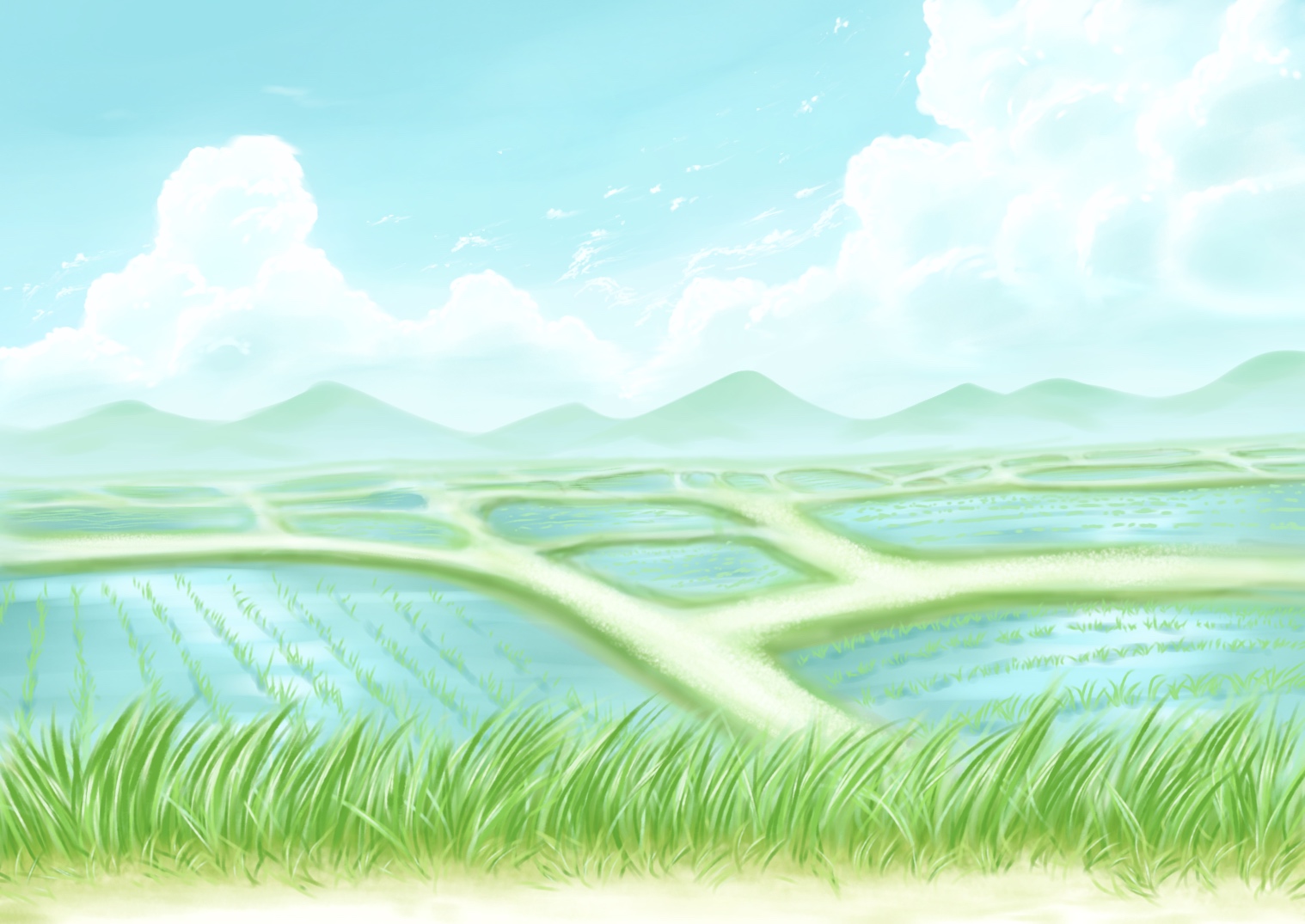
芭蕉はこれらの旅で自然の美しさや人との触れ合い、そして時には無常の世の流れ、古の想い等を受け取っていき、「俳句」の持つ伝える力に深みを与えていったのです。
そして【不易流行(ふえきりゅうこう)】という俳風を新しく考案します。
これは「いつまででも変わらない本質的なものの中にも新しい変化をもとめていく」という考え方になります。
まとめ
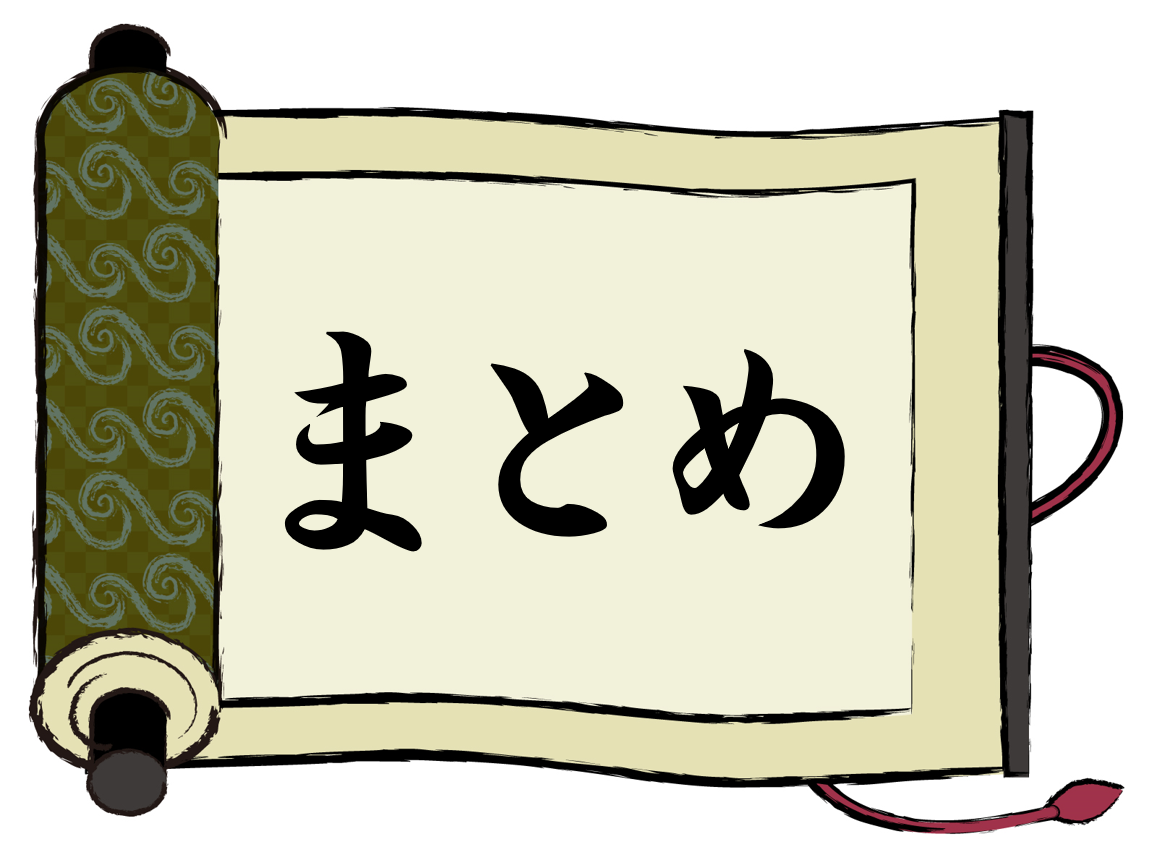
✔ “奥の細道”は松尾芭蕉が書いた紀行文のこと。
✔ 松尾芭蕉は江戸元禄期の有名な俳人。
✔ 芭蕉は45歳の時に弟子の曾良を連れて旅に出発した。
✔ “奥の細道”の旅は江戸の深川から日光、平泉、山形、新潟とめぐり大垣まで、全工程:距離2400km、約150日間の旅であった。
✔ 芭蕉は言葉遊びや滑稽が売りの『俳諧』に心情を入れ情緒豊かな文芸へと高め、芭蕉の俳諧は「蕉風俳諧」と言われた。
✔ 旅の後、新しい考え「不易流行」を俳風へ取り込んでいくようにした。
✔ “奥の細道”は芭蕉の死後まとめられた紀行文となるが、その伝える力で今日も日本国内のみならず海外でも人気が高い。