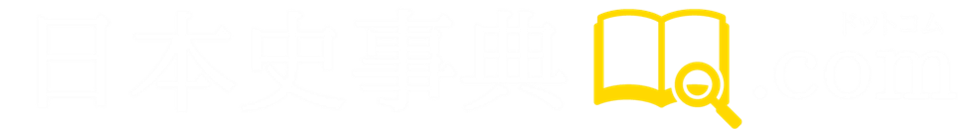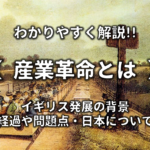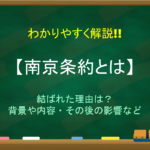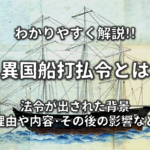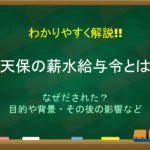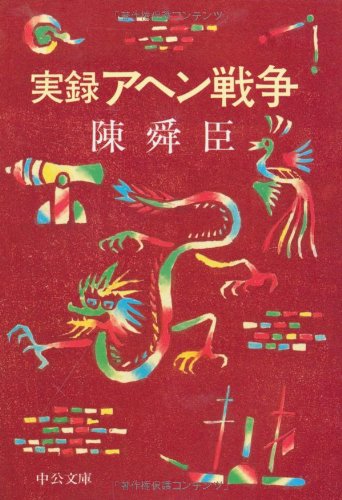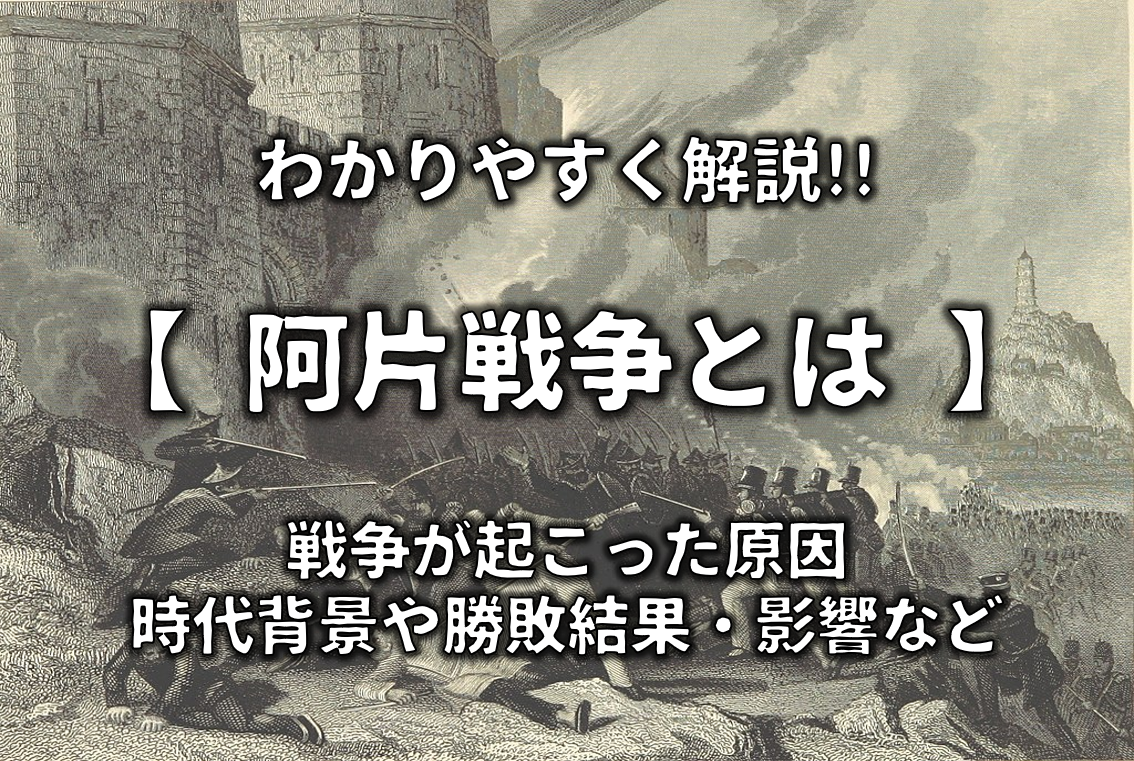
現代では麻薬は当然犯罪です。絶対にやってはいけません。
しかし、一昔前の19世紀ではイギリスは清に麻薬を売りまくって大儲けをしたことがありました。
今回はアヘンが原因で起こった戦争『アヘン戦争』についてわかりやすく解説していきます。
目次
アヘン戦争とは?

(アヘン戦争 出典:Wikipedia)
アヘン戦争とは、1840年(天保12年)に起きた清とイギリスとの戦争のことです。
この戦争は清にアヘンの密輸販売で大儲けしていたイギリスと、禁止していた清との間で2年間行われ、イギリスが勝利を収めました。
この戦争以降、清は欧米諸国の言いなりになってしまいました。
そもそもアヘンって何?

アヘンはケシの果実から取れる麻薬のことです。
アヘンは古代ギリシャから鎮痛剤として使われており、麻薬としてはあまり使われていませんでした。
しかし、アヘンはモルヒネなどの強い依存性がある成分が入っており、使いすぎると最終的には禁断症状で廃人同然になるという恐ろしいものでした。
アヘン戦争が起こった原因

①紅茶の大流行とイギリスの苦悩
アヘン戦争が起きる少し前、イギリスは産業革命を起こして急激な近代化を成し遂げました。
しかし、イギリスは近代化することはできましたが、衛生環境や民衆の生活はどんどん酷くなっていきます。
そこで民衆がこぞって飲んだのが紅茶。紅茶には眠気を覚ます成分であるカフェインが入っており、さらに砂糖を入れると疲れが取れるようになりました。
そういう理由があって産業革命に以降イギリスの人たちは紅茶を飲むことが大流行するようになります。
イギリスでは紅茶を飲むようになりましたが、イギリスは寒いため紅茶を育てることはできません。
そこでイギリスは当時紅茶の一大産地であった清と貿易を開始します、
しかし、清はそんなに近代化していませんし、さらに言えば人口が多いため大体のものが自給自足出来るためイギリスの商品をあまり買いません。
商品を買わなければお金がどんどん清に流れていき、イギリスは貿易赤字に転落してしました。
②アヘンの売りつけと林則徐

(アヘンを吸う中国人 出典:Wikipedia)
清ではアヘンの吸引の風習が広まっていました。
これに目を付けたイギリスは当時植民地だったインドで栽培したアヘンを清に輸出する事で貿易赤字をなくそうとします。
この貿易の形をイギリス・インド・清の三つのところで貿易をしているため三角貿易といいます。
アヘンを輸出し始めると清ではアヘンが大流行。人口が多かったのもありますが、やっぱり清の民衆は政府からの重い税金で自暴自棄になっていたのでしょう。
そのため、ついにはアヘンの輸入量増加により貿易の立場は逆転。イギリスが黒字となり、清は貿易赤字に転落しました。
清はこのままでは清のお金がどんどん無くなっていき清が苦しくなってしまう。
そこで政府は林則徐という人を欽差大臣(臨時の官僚の最高職。皇帝代理とも言える)という役職に任命して当時唯一貿易をしていた広州に派遣しました。

(林則徐 出典:Wikipedia)
林則徐はとても清廉潔白な人でアヘンを売っていた商人からの賄賂ものを一切受け取らず、アヘンに対する取り締まりを行いました。
1839年にはアヘン商人たちに「今後、一切アヘンを清国国内に持ち込まない。」という内容の誓約書の提出するように圧力をかけ、これに応じなかった者を国外追放して、今後清にアヘンを持ち込んだら死刑にすると脅します。
さらに清に広まっていたアヘンを全て没収して、没収したアヘンを全部海で処分しました。
アヘン戦争の勃発!戦争の全容

(清軍を蹴散らすイギリス軍)
①イギリスの決断
イギリスは林則徐のアヘンの取り締まりに大変困ってしまいます。
このままでは再びイギリスが貿易赤字になってしまう。そこでイギリスは清に戦争を仕掛けます。
『え!?』となると思いますが、イギリスからしてみたら商品を勝手に処分されていますし、さらに当時はやるかやられるかの時代。
こっちが仕向けなければ滅ぼされるという恐怖の時代でした。
しかし、イギリスにも不安要素があります。
当時清は『眠れる獅子』と恐れられている巨大国家。もしかしたら全く太刀打ちできず負けてしまうかもしれません。
さらに国内では『さすがにそんな理由で戦争を起こしたら国の恥じゃないの?』という人がいっぱいいるため、もし万が一戦争に負けようものなら清の言いなりになってしまう可能性があるという綱渡り状態でした。
しかし、戦争は議会において僅差で可決されてしまい、この議決を受けたイギリスは、イギリス東洋艦隊という艦隊を作って清に向かわせました。
②アヘン戦争の経過
イギリスが戦争を起こしたことにびっくりした当時の清の皇帝である道光帝は、林則徐を新疆という田舎に左遷してイギリスと交渉します。
しかし、イギリスは皇帝が交渉にドタキャンしたことを理由に英国艦隊は厦門、寧波などの華南と呼ばれる地域の沿岸を次々と占領。
陸戦では清が圧倒していましたが、海戦ではイギリスが鉄製の蒸気船なのに対して清は昔の木の帆船だったため清はまったく歯が立ちません。

(沈められた清軍の船 出典:Wikipedia)
そして、清は長江沿岸や首都北京近くの天津に上陸されてしまい、清は戦争する力がなくなってしまいました。
③南京条約

(南京条約 出典:Wikipedia)
もはや勝ち目がない清は仕方なくイギリスと講和条約を結びます。この講和条約を南京条約といいます。
南京条約では公行と呼ばれる制度(特定の商人しか貿易できない制度)を廃止して誰とでも貿易できる自由貿易に変え、これまで開かれていた広州・厦門・寧波の3港に加えて福州・上海を加えた5港を自由貿易港と決めました。
さらに清は2180万ドルという莫大な賠償金と香港のイギリスに割譲するなどを決めました。
アヘン戦争の影響

①清の場合
アヘン戦争によって清の権威は地に堕ちてしまいました。
ここから先、清は欧米諸国の言いなりとなり、さらに国内では増税の影響で太平天国の乱という大反乱が起きて国内情勢は一気に不安定となってしまいます。
清はもはや国としての機能はほとんどなくなり、日清戦争以降は欧米諸国の半植民地となってしまいます。
そこにはかつて『眠れる獅子』と恐れられてきた清の姿はもうありませんてました。
②日本の場合
アヘン戦争の衝撃は日本にも伝わります。
日本はアヘン戦争が起こる前までは異国船打払令という外国の怪しい船を見かけたら、すぐさま大砲をぶっ放して追い払うという方針でした。
しかし、アヘン戦争で清がボロ負けしたことを受けて天保の薪水給与令という外国の船を見かけたら燃料と食料を与えるという方針に変わりました。
さらに国内では海軍の増強を進めるべきという意見が出始めて、薩摩藩では近代化を進めていくようになりました。
まとめ
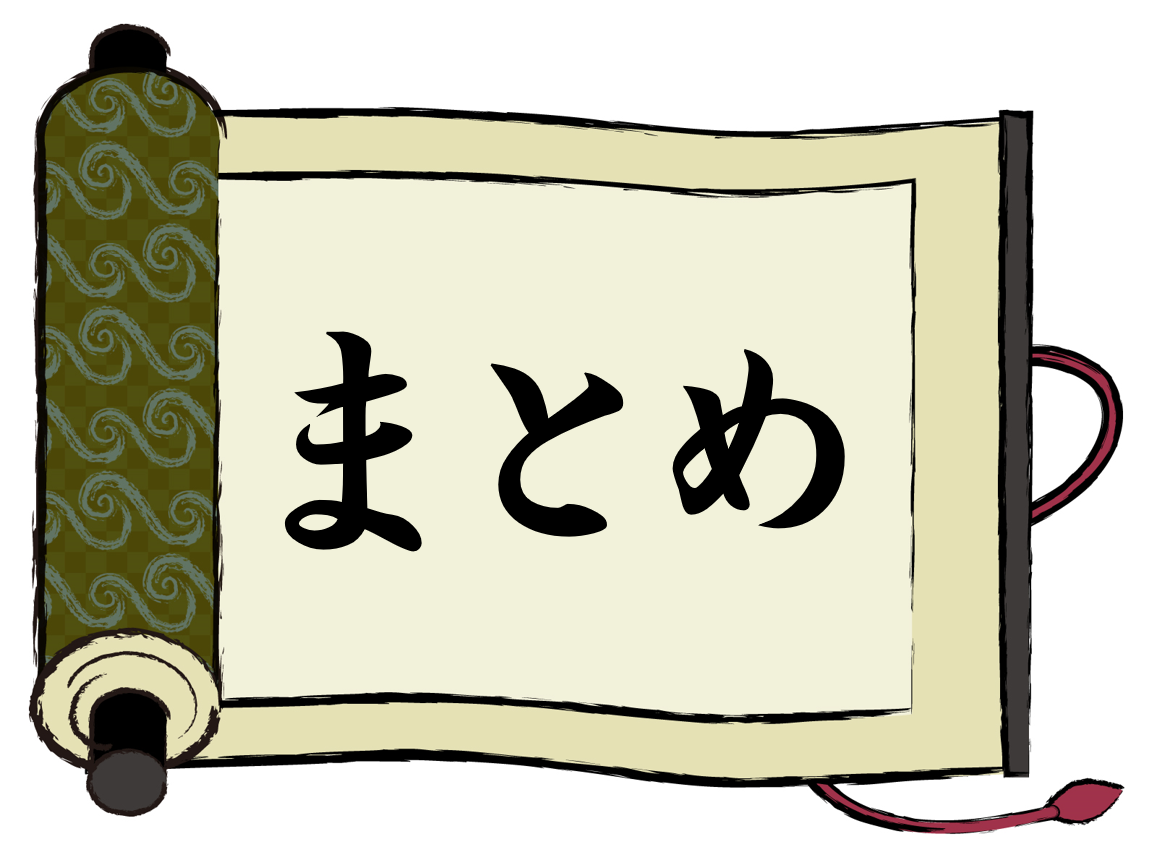
✔ アヘン戦争とは、清がアヘンを処分したことにイギリスが怒って起こった戦争のこと。
✔ アヘン戦争で清はボロ負けして南京条約というイギリスに有利な講和条約を結んだ。
✔ アヘン戦争によって清の権威は地に堕ちて、日本は異国船打払令を廃止した。
阿片戦争のおすすめ書籍!
中国とイギリスのアヘン戦争。
日本では、世界史で少し触れられる程度。
しかし、中国にとってはその後の太平天国の乱と並び、中国の近代の入り口となる重要な事件。
陳舜臣さんの小説「アヘン戦争」を、エッセンスとしてまとめられたもので、流れが掴みやすい内容となっています。
しかし、当時の中国上を理解できていないと、初心者にはわかりづらいのではないかと思います。
前に小説「アヘン戦争」を読んでおくと、中国の歴史と裏舞台が見えてきて、一層面白く読むことができます。
教科書では実にあっさりとした記述でしか触れないアヘン戦争だが、いやあ、おもしろい(無邪気な意味での「おもしろい」ではなく、興味深いという意味)。
これは見方を変えたイギリス史でもあり、黄金のヴィクトリア朝時代の側面を知るうえでも役に立つ。
著者はアヘン戦争に関して大部の小説を書いているが、本書は小説ではなく、豊富な資料によって史実を淡々と追い、アヘン戦争の本質を突いていく。
中国は中華思想の国である。自国は天に等しく、対等な国など存在しない。アヘン戦争の時代、中国は中華思想に染まっており、アヘン貿易をめぐるイギリスの圧力に対抗できなかった。
アヘン戦争は、イギリスがアヘン交易による利益のために起こした、不義の戦争である、というのが著者の立場。
イギリスはインドの産物であるアヘンを中国に売らなければ、インドにおける立場を失いかねなかった、というのが著者の指摘である。
アヘンは口実であって、中華思想の打破が目的だった、という主張を明確に退けている。
この戦争の裏にある、中国人の物の考え方、官僚主義の弊害に対して、林則徐がいかにいかに戦ったかを、簡潔に書いており、とても読みやすい。
現代の日中関係の悪化は、そもそも相手に対する理解が足りないのではないかと思う。日本人はもう少し、中国人の考え方を理解したほうがよい。
アヘン戦争は19世紀の話だが、現代にも絶対役に立つ。